現在、日本が戦争に負けてから70年近い歳月が経過している。
そして、時の経過と共にほとんどの日本人は、米国という戦争に勝った国がつくった「戦後の論理」しか知らなくなってしまった。そして、それすら、風化し始めている様相を示している昨今である。たとえば、日本国憲法第九条を守る、平和憲法を守るという善意の人々が半世紀にわたって熱心に、ここ日本で活動を続けている。彼らは戦後、米国がつくった論理によって誘導され、動かされてきたことさえ、おそらく、一度も意識したことさえない人々が現在では、ほとんどではないだろうか。
「どうして、独立国、日本にいまだにこれだけの米軍基地があるのか。特に沖縄に米軍基地が集中しているのか。」平和憲法を守る人々は、都合良くそのことを忘れて自身の理想主義に酔っているように見えないでもない。もっと意地の悪い見方をするなら、愛すべき、人の良い日本人らしい特性を備える彼らは、戦後、米国が作り出した言語空間の中ですっかり洗脳されてしまったある意味、犠牲者と言う見方さえできるかもしれない。
そうは言っても冷戦が終了し、米国が日本に押しつけた「戦後の論理」の幻想が、米国の国力の低下と共に、いたるところで綻び始めている。そんな時代だからこそ、我々は「戦前の論理:先の大戦に敗北した日本の論理」をもう一度、振り返って冷静に考えてみる必要があるのではないだろうか。
日本には「喧嘩両成敗」という言葉がある。戦争に負けた国にも言い分、大義は当然ある、それがなければ、目的のない戦争を日本は遂行したことになってしまう。戦後、私たちは、注意深く意図的にそれらから遠ざけられ、考えないで済むようにされてきたし、自分たちもそのことになるべく触れないように努めてきた。
「戦前の日本の論理(きちんとそれが構築されていたかは別にして)」、「米国が日本に押しつけた戦後の論理」、この二つを、もう一度、客観的に見直し、考え直すことによってしか、二十一世紀の新しい時代の日本をつくっていくことはできないのではないか。
戦争に負けて残された人々もその中でどんなに苦しくても同じように生き続けていかなければならなかったこともたしかである。当然、いろいろな妥協、自己保身も歴史の現実のなかにはあるだろう。
しかしながらやはり、勝者が東京裁判のような勝者の論理で無理矢理、歴史の連続性を日本人の意識から奪ってしまった事実を、我々日本人は、「二十世紀の欧米人」は少々傲慢過ぎたと考えるべき時期を迎えているのではないのか。
今回は、そういったことを考えるための本を紹介したい。
「日米開戦の真実 大川周明著 米英東亜侵略史を読み解く」(佐藤優・著・小学館・2006年)と参考資料としての「日本の失敗~「第二の開国」と「大東亜戦争」~」松本健一著である。
まず、一冊目の目次と一部要約から読んでいただきたい。
<目 次>
第1部米国東亜侵略史(大川周明)
第2部「国民は騙されていた」という虚構(佐藤優)
第3部英国東亜侵略史(大川周明)
第4部 21世紀日本への遺産(佐藤優)
第二部「国民は騙されていた」という虚構について
日本国民は何について誰に騙されていたというのであろうか。「客観的に見れば国力の違いからアメリカと戦っても日本は絶対に勝つはずがないのに、アジア支配という誇大妄想を抱いた政府、軍部に国民は騙されて戦争に突入した」という見方が現在では、ほぼ常識になっているが、これは戦後作られた物語であると佐藤氏はこの本で述べている。
さて、第二部ではまず、第一章 大川周明が東京裁判をどのように見ており、占領軍がいかに大川を危険視していたか、第二章 アメリカによる日本人洗脳工作がどのように進められたか、第三章 アメリカの対日戦略を分析するに大川周明の「米英東亜侵略史」を見直す必要があるとなっている。
東京裁判について
佐藤氏はまず大川周明が戦争突入時の首相であった東条英機らと「平和に対する罪」ということでA級戦犯として日本占領軍から起訴された法廷での奇異な行動について解説している。それによると、たしかに大川について本当に精神錯乱状態に陥ったのか、それともそれを装ったのかいろいろと議論の余地はあるが、極東軍事裁判で起訴され、収監された人たちの証言から佐藤氏は、大川は一時的にも精神や体に変調をきたしたのではないかと結論づけている 大川は裁判の対象からはずされ、病院を転々として治療を受けた。物事の善悪が判断できる状態になれば公判にもどすのが通例であるが、半年にわたる精神鑑定の結果、大川の精神状態は正常ということになったが、軍事法廷は大川周明を裁判から除外した、そして彼は松沢病院から1948末に自宅に戻った。大川が法廷で裁かれなかった理由として次のように解説している。
大川は腹の底から法廷をバカにしており、戦勝国の裁判官による「公平な裁判」などというのは作り話で、暴力を背景にした軍事裁判を批判するためには、法廷を悲喜劇の劇場にする方が、効果があると考えていたのが大川だった。だから彼を、裁判からを除外した方が東京裁判の権威が保てると占領軍が考えたというものだ。
論理の言葉でアメリカ、イギリス、ソ連などの嘘が崩されることを占領軍が恐れたのかもしれない。
アメリカによる日本人洗脳工作について
日本国民が開戦当時の政府・軍閥に騙されて勝つ見込みのない戦争に追いやられたというのは戦後のアメリカによる洗脳工作によって、戦後になってから、作られた神話であるという。そしてこの神話が作られる過程で、中国を含むアジア諸国を欧米の植民地支配から開放するという日本人がもっていた大義は、日本の支配欲を隠す嘘だという“物語”が押しつけられ、その呪縛から未だに私たちは逃れられずにいる。
また、日本は当時抑圧されていたアジア諸民族の解放、そしてアジアを植民地にしなくては生きていけないという道徳的に悲惨な状況に置かれた欧米人を解放することを考えていたのであると佐藤氏はいう。さらにアジア、ヨーロッパがそれぞれの文化を基礎に、かなりの程度完結した世界を作り、棲み分けていこうというのが大東亜共栄圏の基本的な考え方だったと大川の多元主義の立場を説明している。
戦後アメリカが対日占領政策で巧みに取り入れたのがイギリスの手法である。イギリスは占領地域を徹底的に打ちのめすことをせずに、余力と名誉を保持し、イギリスの世界支配システムに組み込んだという手法である。アメリカが効果を挙げたのは、GHQの指導で行われた「真相箱」という工作である。「真相箱」では、悪いのは軍閥、その中でも陸軍、その親玉が東条英機首相という構成になっており、東条が日本国民を騙した大悪党であると断罪すると連合国側が主張する。
大川のアメリカ対日戦略分析について
戦後アメリカによって「教育」された内容を棚にあげて、「米英東亜侵略史」をテキストとして大川が主張する日米開戦の論理を明らかにしている。
彼は日米戦争開戦の16年前に出版した著作『亜細亜・欧羅巴・日本』の中で戦争の不可避性を述べている。世界には複数の世界がお互いに切磋琢磨するのが世界史であり、具体的には東洋という世界と西洋という世界が競争し、その過程で戦争は不可欠であるとの認識を示している。
それではアメリカの対日戦略はどうだったのか。アメリカが提唱した中国の門戸開放とは、植民地の分配に自国を参加させよということである。仮に中国が列強によって分割されることになれば、アメリカの取り分が少なくなるから、領土保全の方が都合のよい利権構造を維持できるという計算からの意思表示に過ぎない。日本はアメリカのこの意図に永い間気づかなかったという。
アメリカの満鉄買収政策はきわめて大規模な計画の一部であったという。その計画とは、満鉄を手に入れ、ロシアの疲弊に乗じて東支鉄道を買収し、こうしてシベリア鉄道を経てヨーロッパに至る交通路を支配し、鉄道の終点大連、浦塩から太平洋を汽船でアメリカの西海岸と結び、大陸横断鉄道で東海岸に至り、東海岸から船で大西洋をヨーロッパと結ぶ交通系統、すなわち世界一周船・車連絡路をアメリカの手に握る第一歩として満鉄を日本から買収しようと計画したと大川は『米英東亜侵略史』で述べている。
当然、アメリカの満鉄買収計画を粉砕した日本に対し、日本がアメリカの太平洋制覇と中国進出を妨げる主な障害と考えるようになってくる。この後アメリカで反日感情が高まり、日系人のカリフォルニア州内の土地所有禁止、移民法の改正と発展する。
一方、アメリカの国益のためには海軍力の増強が必要で、フィリッピンやガム島に海軍基地を建設し、欧米列強と軍事的に対峙する力のあるアジア唯一の国、日本と軋轢をもたらすことは必然的だったと大川は考えていた。しかし、欧米列強の植民地にならなかった日本は、中国を含むアジアの諸民族を植民地支配のくびきから解放しようと真剣に考えて行動したが、後発帝国主義国である日本は基礎体力をつけるため、期間を限定して、アジア諸国を日本の植民地にすることはやむを得ないと考えた。ここに大川の限界が見られ、日本人の民族的自己欺瞞が忍び込む隙ができてしまったと佐藤氏はいう。
ところで、大川周明氏といえば、東京裁判のA級戦犯の一人であり、法廷で東条英機の禿頭を後ろからパシッと叩いたことで有名である。ドキュメンタリー番組で見た人も大勢おられるのではないか。結局、彼は精神病扱いされ、法廷を離れて入院。その後コーランを全巻和訳するなどの仕事をした。この本の副題に『大川周明著米英東亜侵略史を読み解く』にあるように、太平洋戦争開戦直後、大川周明氏はNHKラジオで、連続講演を行った。米英となぜ開戦にいたったかを冷静に分析して、国民に納得させるためのものである。それが本としてまとめられたのが、「米英東亜侵略史」である。佐藤優氏は、これをアメリカ編、イギリス編と分けて全文を紹介し、本書で解説している。
よく歴史や政治を解析するためには、現代日本では死語になっている「地政学」をよく理解しないといけないということが言われる。
現在に通じるアメリカの本質について、大川周明は「アメリカの二重外交:ダブルスタンダード」と鋭く見抜いていた。
米国の変質がはっきりと表に見えたのは第1次世界大戦であった。「戦争はアメリカの自尊心が許さない」と孤立主義を対外的には標榜していたが、連合国側の勝利が確定するや、「自らの利権拡大」のために大きく国家方針を変えていった。「自由」「独立」を標榜するアメリカが、帝国主義国家の顔を剥きだしにしてきたのである。
一方日本においても、明治維新時以降、1920年代の普通選挙制度、腐敗政党と、財閥の利権の拡大と政治経済の腐敗も目に付き始めた。大川周明は、そんな日本国の「国家改造」を企てた男でもあった。(「猶存社」の三尊と呼ばれた北 一輝、満川亀太郎は大川と違い日米非戦論であったことも興味深い。彼らには大川にはない政治的戦略思考能力があった。その意味で大川周明は政治的人間ではない。)
*猶存社(ゆうぞんしゃ)
老壮会の急進的右派思想家の満川亀太郎を中心に、1919年8月1日に結成された国家主義運動の結社。社名は『唐詩選』の巻頭にある魏徴の詩「述懐」にある「縦横計不就 慷慨志猶存」にちなむ。
1920年7月には、機関誌『雄叫び』を発行。皇太子裕仁親王の渡欧阻止や宮中某重大事件で活動し、安田善次郎・原敬らの暗殺事件にも思想的な影響を与えたといわれている。中心スローガンは「日本帝国の改造」と「アジア民族の解放」であった。
また同人による学生運動の指導により、日の会(東京帝国大学)・猶興学会(京都帝国大学)・東光会(第五高等学校)・光の会(慶應義塾大学)・烽の会(札幌農学校)・潮の会(早稲田大学)・魂の会(拓殖大学)などの団体が生まれた。
天皇観の相違やヨッフェ来日問題をめぐって、北と大川・満川との対立が激しくなり、1923年3月に猶存社自体は解散・分裂した。
その後、1925年に大川は、満川、安岡正篤らと行地社を結成した。一方、北の影響を受けた清水行之助は大行社、岩田富美夫は大化会を結成している。
もともと、米国には、国内発展を優先させる有名な「モンロー主義」があり、自国の裏庭である南北アメリカ大陸諸国への干渉や働きかけを排除するかわりに、他国のことにも不干渉を原則としていた。
ところが、国内利益を確立した第1次大戦が終結した時期から、覇者の英国に成り代わろうという戦略行動を露骨にとってきた。
「アメリカは本音(帝国主義)と建前(道義)を使い分ける二重構造(ダブルスタンダード)は、道義国家である日本には受け入れられないと大川は考えた。」(P135)
民族自決を標榜したウィルソン大統領の提唱で国際連盟は発足したが、当のアメリカ自身は加盟しなかった。
国際連盟は、日本が提唱したアジアやアフリカでの人種差別の禁止要項はにべなく拒絶したことも日本人は忘れてはならない。
結局、アメリカは国際連盟には加盟せず、しかし、その権能は利用し、満州国の調査を行い、日本による満州国独立を国際連盟には承認させなかった。日本はその結果を不服として1933年に国際連盟を脱退することになる。
大川周明は「アメリカという病理現象を治癒することが日本の使命である」とまで言明している。
佐藤優氏はこう解説している。
「筆者は見るところ、大川周明は軍事行動で日本がアメリカやイギリスに勝利することは不可能と考えていた。
むしろ戦争を契機に日本国家、日本人が復古的改革の精神で団結し。アジアの同胞から信頼され、新たな世界をつくる世界システムを作る端緒を掴めば、そのときに軍事力以外の力でアメリカ、イギリスとの折り合いをつつけることができる可能性があるという認識をもっていたのではないかと思われる。」(P139)
「国際問題を論ずる識者は、理念先行の非現実的平和主義者と、国家の軍事力や経済力だけに目を奪われ、道義性を冷笑する力の論理の信仰者の陣営に分かれがちであるが、大川はそのどちらにも属さない。 道義性とリアリズムを大川なりの方法で統合しようとしているのである。」(P140)
「大川の限界は米英東亜侵略史の後半部分で明らかになる。近代化において欧米列強の植民地にならなかった日本は、中国を含むアジアの諸民族国を植民地のくびから解放しようと真摯に考え、行動した。
しかし、後発帝国主義国である日本は基礎体力をつけなくてはいけない。そのために、期間を限定して、アジア諸国を日本の植民地にすることは止むを得ないと考えた。
ここに日本人の民族的自己欺瞞は忍び込む隙ができてしまった。
あなたを痛みから解放するために、あなたに一時的に痛みを加えますというのは外科手術が前提としている論理であるが、これを国際政治に適用した場合、痛みを追加的に加えられた民族にその理由は理解されないのである。」
「イギリスのような老獪な帝国主義国は、植民地住民の人権などははじめから考えておらず、また植民地は帝国を維持するために不可欠と考えていた。
そのために植民地住民に対する圧迫をほどほどにしていた。相手にどの程度の痛みがあれば、どの程度の反発があるかということを冷徹に計算していたのである。
植民地支配の打破を真剣に考えていたからこそ、日本はアジア諸国に痛みを与えていることに気がつかなかった。ここに大川のみならず。高山岩男や田邉元といった京都学派の優れた思想家が落ちていった罠があったのだ。」(P141)
また歴史において「もっとも競争に強い国は自由貿易を相手国に強要する」「19世紀のイギリスが提唱した自由主義。21世紀のアメリカが提唱している新自由主義(小さな政府)なども同じ考え方であろう。
大川周明は多元主義者
「社会主義革命はヨーロッパの精神的伝統から生まれた改革であるため、精神的伝統を異にする日本を含むアジアでは改革は自国の伝統を回復し、自国の善によって、自国の悪を克服することによってのみ可能だという信念をもつ大川は、社会主義をアジアの適用することに関しては批判的なのである。」(P237)
また佐藤優氏は、左翼イデオロギー(大ブント構想など)哲学者の広松渉氏の主張にも注目している。
「東亜共栄圏の思想は、かつては右翼の専売特許であった。日本の帝国主義はそのままにして、欧米との対立のみが強調され、今では歴史の舞台が大きく回転している。
日中を軸とした東亜の新秩序を!それを前提とした世界の新秩序を!これが今では日本資本主義そのものの抜本的統御が必要である。が、しかし官僚主義的な圧制と腐敗をと硬直化を防げねばならない。
だがポスト資本主義の21世紀の世界は、国民主権のもとに、この呪縛の輪から脱出しなければならない。」(P250)
「EUは中世から培われたユダヤ・キリスト教の一神教。ギリシャ古典哲学。ローマ法の三原理が一体となった「コルプス・クリスチアヌム」(キリスト教世界)という共通の土台があってはじめて出来たものだ。
ローマ法を欠くロシアはEUの共通意識をもてないのである。
「コルプス・クリスチアヌム」に争闘する共通意識は東アジアには見当たらない。しいて言えば、新旧漢字文化圏というのであろうが、それは中華帝国に日本が吸収されることを意味するので、日本の国益に合致しないと考える。
かつて日本は、大東亜共栄圏という形で人為的に、共通意識の理念型を東アジアで構築することを試みたが、失敗した。この教訓からも学ばなくてはならない。
佐藤氏の理解では、地域共同体には「共通意識の理念型」の要因と。「力の均衡の論理」の双方の要因が内在しているが、「共同意識の理念型」に軸足を置かない共同体構想は不安定だ。」(P256)
大川周明は「大和心によって、支那精神とインド精神を統合したのが東洋魂である」と言ってはいるが・・・・。
佐藤優氏は、現在の日本もおかれている厳しい現実を国民各位が凝視することから始まらないといけないとも述べている。
「太平洋を挟んでアメリカという帝国を隣国にしてしまった運命を日本人は受け入れなければならない。その現実、あるいは制約の中で外交を展開することが日本の国益に適う」と佐藤氏は考える。
「対中牽制を睨んで日本の外交戦略を「力の均衡の論理」に基づいて組み立てなおすことが急務だ。
具体的には、日米同盟の基礎の上で日本がインド、ロシア、モンゴル、台湾、ASEANと提携し、中国を国際社会の「ゲームのルール」に従わせ、日本の国益の増進を図るための連立方程式を組むことだ。
そこで切磋琢磨しているうちに、自ずから、共通認識の理念型が生成してくるかもしれない。しかし、それにはまだまだ時間がかかる。われわれには必要なのは、アメリカという超巨大大帝国と中国という急速に国力を強化しつつある国家の間にある地政学的運命を冷静に受け止め、日本国家と日本人が生き残っていく方策を真剣に模索することだ。」(P258)
大川周明はユニークな思想家
「大川の人間観が性善説、性悪説のいずれにも立脚せずに、無記の立場から突き放して人間を観察していることに基づく。」
「大川は、民主主義であれ、共産主義であれ、思想の背景にはそれを生み出した伝統と文化があるので、それを無視して日本や中国に輸入することは不可能と考えていた。
北一輝を含む多くの日本の国家主義者が孫文の国民革命に感情を揺さぶられたのに対し、大川周明は距離を置いた姿勢を示す。大川は孫文の三民主義の基礎となる民主主義(デモクラッシー)自体が欧米的原理であって、アジア解放の手段にならないと考えていた。
ちなみに共産主義も大川にとってはロシア的原理なので共産主義がアジアを解放することはできないと考えている。」(P274)
本書における佐藤優氏の「大川周明」を参考書とした結論は
現在、流行の新自由主義やグローバリゼーションには歩止まりがある。
どうやって日本の国家体制を強化するかがわれわれに残された現実的シナリオだ。
国家体制の強化は、大川周明が言うように、日本の伝統に立ち帰り、「自国の善をもって自国の悪を討つこと」によって可能になる。そして自信をもって自国の国益を毅然と主張できる国に今なることだ。
自らの主張に自信を持っている国家や民族は、他国や他民族の価値を認め、寛容になれる。日本はアメリカの普遍主義(新自由主義や一極主義外交)に同化するのでもなければ、「東アジア」の共通意識を人為的に作るという不毛なゲームに熱中する必要もない。
佐藤氏の解説にはいろいろご意見があるだろうが、大川周明氏を東条英樹の禿頭を東京裁判で殴った男という記憶で終わらせるのはあまりにも歴史について不遜であろう。
*大川 周明(おおかわ しゅうめい、1886年12月6日 – 1957年12月24日)
日本の思想家。 1918年、東亜経済調査局・満鉄調査部に勤務し、1920年、拓殖大学教授を兼任する。1926年、「特許植民会社制度研究」で法学博士の学位を受け、1938年、法政大学教授大陸部(専門部)部長となる。その思想は、近代日本の西洋化に対決し、精神面では日本主義、内政面では社会主義もしくは統制経済、外交面ではアジア主義を唱道した。晩年、コーラン全文を翻訳するなどイスラーム研究でも知られる
*参考資料として 「日本の失敗~「第二の開国」と「大東亜戦争」~」松本健一著の松岡正剛氏の解説以下。
http://www.isis.ne.jp/mnn/senya/senya1092.html


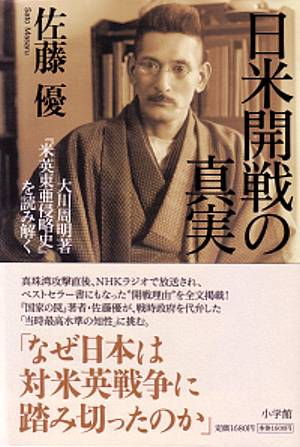

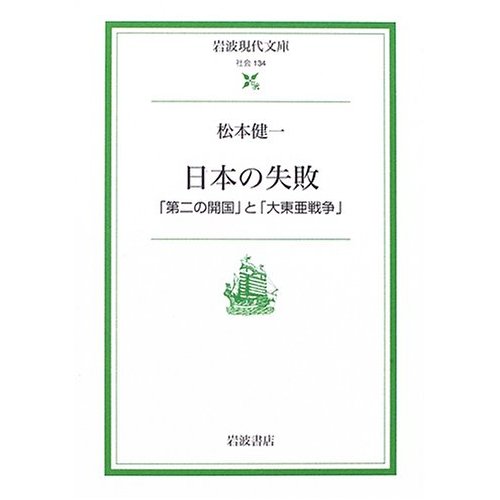
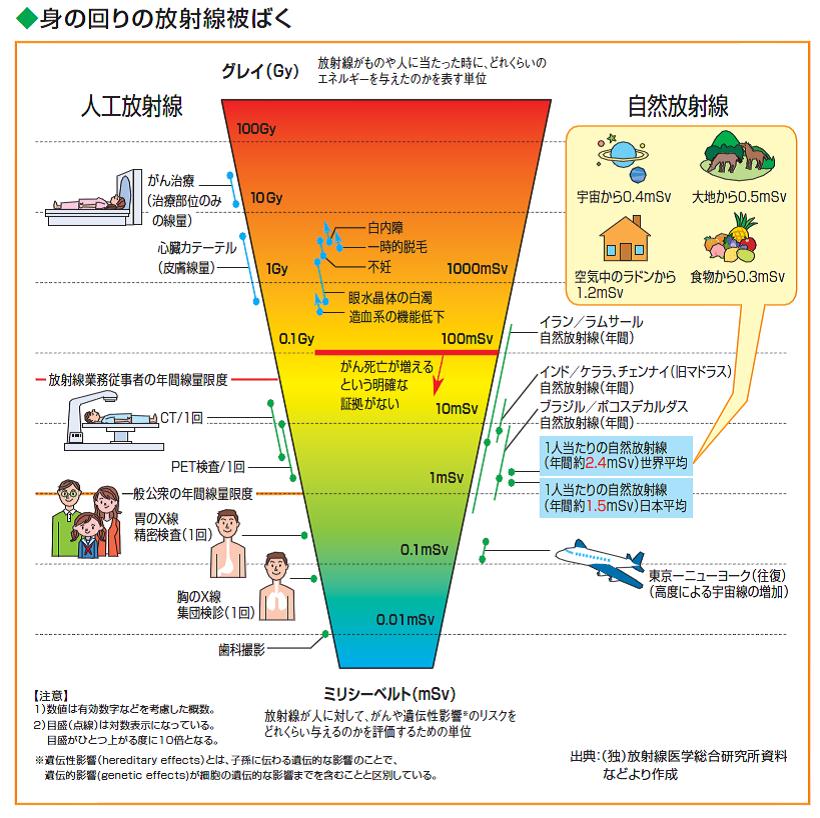

 Follow me on Twitter
Follow me on Twitter